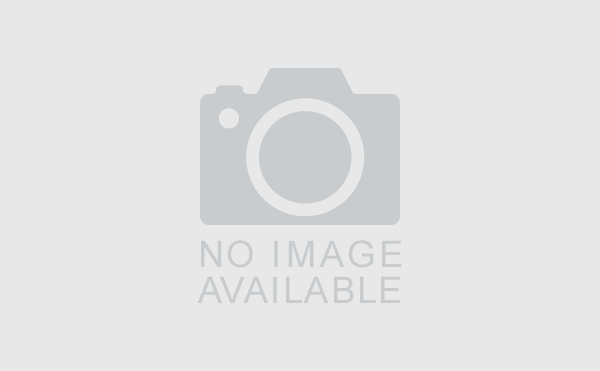オンラインで「故郷」授業(第1~3時)
勤務校では2学期始まりの1週間、登校とオンライン授業を選択できるようにしました。
ご紹介する「故郷」の授業は、第1~3時がオンラインベースの授業、第4時からが教室での授業となります。教室での授業も、話し合いや黒板への発表を控えて、タブレット端末を活用しました。参考までに、使用したプリントもあげておきます。
(第1時)①オンライン会議の仕方の説明、②リフレクションシート記入、③漢字語彙プリント(宿題)
1学期にTeamsは使っていましたが、会議機能は未使用でした。よって、会議機能の使い方(背景を変える、背景を消す、マイクのオンオフ、スピーカーのオンオフ、チャット)に加えて、複数の作業ができるようウィンドウの最大化・最小化などを、パワポ画面を共有しながら丁寧に説明しました。また、こうしたコンピュータ活用スキルが重要になってくることを教え、今は苦手でもしっかり身に付けていくよう指導しました。これだけで30分が経過。残りは共同編集のリフレクションシート(他記事参照)を記入し、事前に配っておいた「漢字語彙プリント」を進めるように話しました。この日のリフレクションには、「パソコンの操作を身に付けていきたい」という前向きな感想がたくさん見られました。
(第2時)①前時のリフレクション共有、②現代の日本社会について考える、③「故郷」朗読、④リフレクションシート記入
前時のリフレクションの中から、面白いものをいくつか紹介しました。リフレクションの内容が他の模倣になったり、マンネリ化したりしないよう、活性化していく狙いもあります。
次にやったのは、現代の日本社会について考える、という課題です。これを最初に入れることで、近代の中国社会との共通点や相違点を捉えながら、自分の意見を形成させていきます。修学旅行が延期になった生徒たちは、相当不満がたまっているようでした。だから、「悪い点はマスコミやインターネットで盛んに言われているね。良い点もしっかり見つけることが、「多角的に物事を見る」ということだよ。」という話もしました。これらの意見は、プリントに書かせたのち、Teamsのチャネルの掲示板に記入させました。
「故郷」の朗読ですが、当初はCDを再生する予定でしたが、音質が悪く断念。自分で朗読しました。その際、自分で黙読したい生徒は、パソコンの音量を下げるように指示しました。(私もそうですが、朗読を聞きながら文章を読んでいくのが苦手な生徒もいます。) この日は、「旦那様!」までしか読めませんでした。リフレクションには、「自分たちが生きている日本社会について考えることが新鮮だったし、楽しかった」という意見が多く見られました。
(第3時)①前時のリフレクション共有、②「故郷」朗読の続き、③小説の設定まとめ、④リフレクションシート記入
「故郷」の朗読を終えたあと、小説の設定について分析していきました。人物相関図は、本当はペア学習を取り入れたいところですが、オンラインなので不可。自分で作成させてから、私の作ったものと比較させました。「故郷」は内容理解でつまずく生徒も多いため、この人物相関図が役に立ったという感想が多くありました。また、登場人物を重要だと思い順番に並べ、その理由を述べるという活動も入れました。この交流も掲示板機能を使っています。
この授業の肝となるのが、主人公の年譜づくりです。年譜を作ってみると、ルントウと関わったのは10歳時の、たった数日間であることが分かります。リフレクションにも、そのことに対する驚きが書かれていました。
投稿者プロフィール
- 都内公立中学校教諭
- 本サイトの管理をしています。運営に関してアイディア等があれば、是非お寄せください。
最新の投稿
 未分類2023.08.07生成AIは創作できるか ~AIの成長~
未分類2023.08.07生成AIは創作できるか ~AIの成長~ ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(2)
ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(2) ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(1)
ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(1) 関心・意欲・態度2021.09.05ICT活用で「故郷」授業(第4~5時)
関心・意欲・態度2021.09.05ICT活用で「故郷」授業(第4~5時)