絵本を批評しよう ―「おおきなかぶ」と「スイミー」を読みくらべよう―
中学3年生の「読む」では、作品を批評する力が求められます。その練習を絵本で行う授業を作ってみました。
批評とは、対象を客観的に分析し、自分の評価を述べることです。この活動が成立するには、対象を分析する力と、分析したことを記述する力が不可欠です。これらを身に付けさせるスモールステップとして、以下のような工夫を行いました。
- 誰もが一度は読んだことのある絵本を扱う。
- 絵本は読み聞かせた後、本文を配る。※批評はあくまで、絵本の本文を対象とします。
- 同一テーマの、異なる2作品を比べ読みさせる。※ここでは「協力」をテーマとする「おおきなかぶ」と「スイミー」を取り上げています。
- 批評の観点を提示する。※ワークシート参照
- 作品を評価する状況を設定する。※4歳の子どもの誕生日に買い与える絵本として、どちらを選ぶか。
- 作文の型を提示する。
- 互いの批評文の分かりやすさや説得力について話し合う。
私は、古典作品の批評をしたくて、この授業を中学2年生で行いましたが、書くのが苦手で普段はなかなか書けない子どもも、スラスラと書くことができていました。絵本の読み聞かせを、子供たちが喜んで聞いていたのも新鮮でした(笑)
細部を変えれば、小学5年生くらいから実践できる内容だと思います。ワークシートはこちら。絵本を批評しようワークシート
投稿者プロフィール
- 都内公立中学校教諭
- 本サイトの管理をしています。運営に関してアイディア等があれば、是非お寄せください。
最新の投稿
 未分類2023.08.07生成AIは創作できるか ~AIの成長~
未分類2023.08.07生成AIは創作できるか ~AIの成長~ ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(2)
ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(2) ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(1)
ICT2023.08.07生成AIに読書感想文は書けるか?(1) 関心・意欲・態度2021.09.05ICT活用で「故郷」授業(第4~5時)
関心・意欲・態度2021.09.05ICT活用で「故郷」授業(第4~5時)
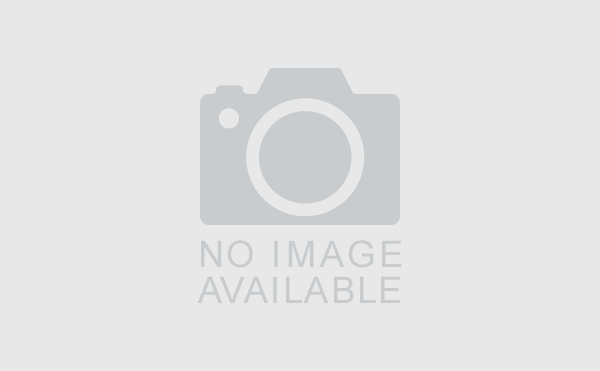
先日、研究会で発表して以下のようなご指摘を受けました。
①比較が批評になるのか。
②4歳の子どもに何が適しているのかをまず考えさせ、情報を共有させた方がよい。
③「観点」は「読むための観点」なのか、「批評の観点」なのか。
④「観点」は「観点例」としたほうがよい。
⑤作文の型として、「どちらが良い」では、あらさがしになってしまう可能性がある。
深めさせるのが目的であって、「どちらも」や「どちらでもない」という選択肢があっても良いのではないか。
①については、私たちは対象の価値を考えるときに、少なからず比較を行っている、という指摘もありました。更に、対象となる分野に関する知識が不足していれば、対象を客観的に評価することなど不可能です。それは、オリンピックでカーリングを見始めた私が、プレイの良し悪しが分からないのと一緒ですね。
⑤については、感想文と批評文の違いということも話題になりました。相手意識をもって、読み手を説得しようとするのが批評文ということです。だから、必ずしも論理性にこだわらなくても良いのではないか、というご指摘も受けました。